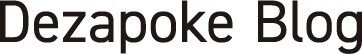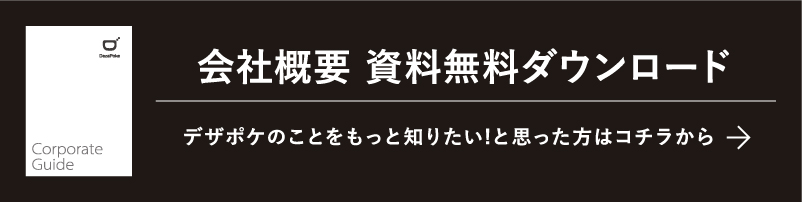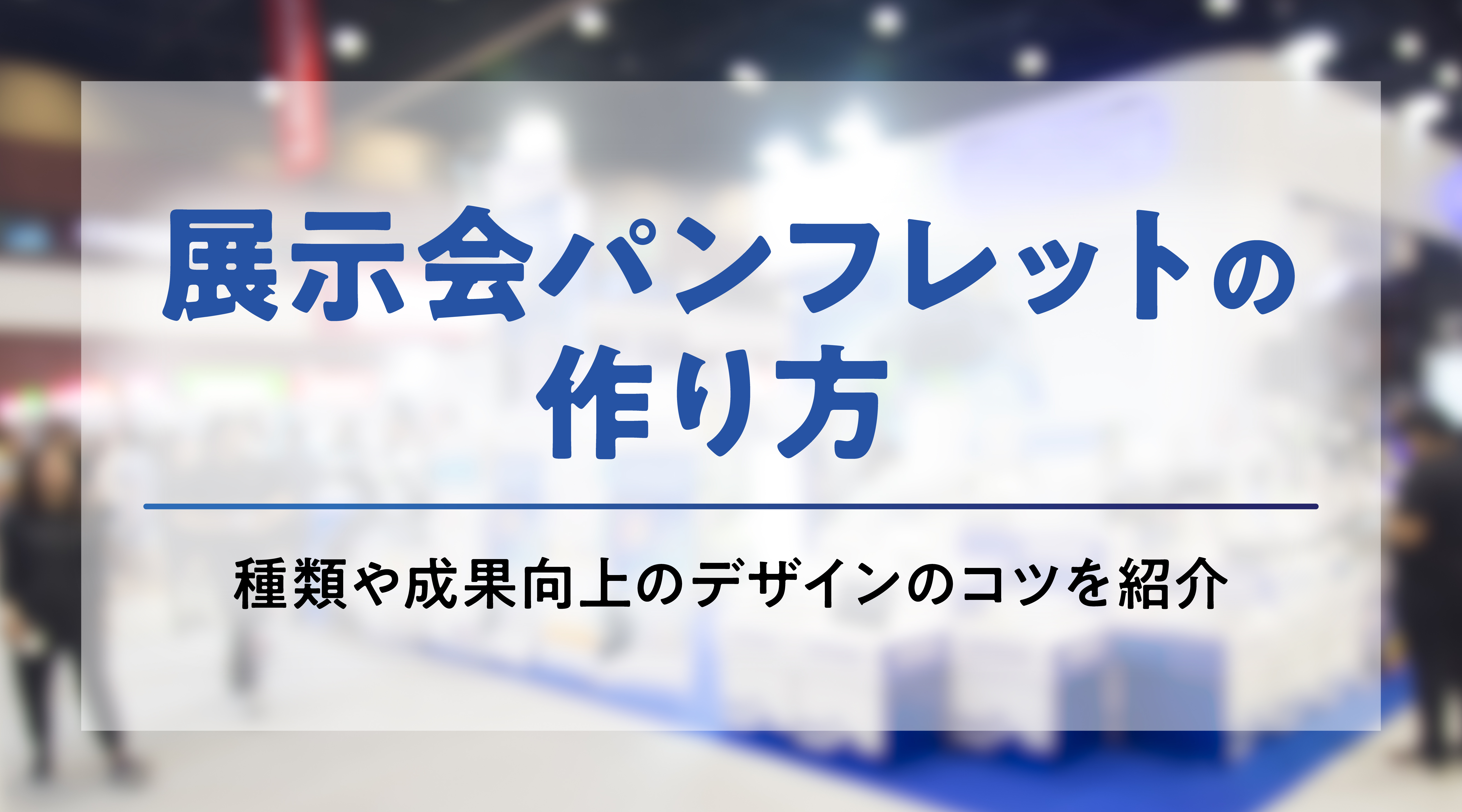
展示会パンフレットの作り方|種類や成果向上のデザインのコツを紹介
展示会に出展しても期待通りに商談に繋がらない場合、その原因はパンフレットの設計にあるかもしれません。

来場者にその場限りで終わらず、その後もお客様の心に残り、継続的に興味を持ってもらうには、伝わりやすいパンフレットのデザイン設計が鍵となります。
目次
展示会におけるパンフレットの効果・重要性
展示会におけるパンフレットは、以下の効果・重要性が見込めます。
■ 顧客との長期的な関係構築の第一歩となる
■ 信頼性・専門性を伝えることができる
■ 効率的に営業活動ができる
BtoB取引は検討期間が長いため、展示会後も手元に残るパンフレットは関係構築の維持に役立ちます。
また、媒体を通して自社の強みである技術力・実績・導入事例などを伝えられるため、お客様からの信頼獲得に繋げることができます。
効率面では、商品やサービスに関する詳細をパンフレットに委ねられるため、シンプルに対応数を増やすことができ、省スペースで導入することができるため、他の展示物や商談スペースを圧迫することもありません。
展示会におけるパンフレットの種類 製本を解説
展示会のパンフレットは、目的や来場者の関心度合いに応じて使い分けることが重要です。
ではさっそく、パンフレットにはどのような種類があるのかをご紹介していきます。
中綴じパンフレット|確度の高い見込み顧客向け
中綴じパンフレットとは、複数ページで構成される背表紙のない小冊子です。

根元まで開ける構造のため、左右にまたがった、見開きのレイアウトデザインができるのが特徴です。
製本方式や一般的なサイズは以下の通りです。
| 製本方式 | 一般的なサイズ | デザインの自由度 |
| 紙を重ねて製本するため4の倍数のページ数 真ん中をホチキスで綴じて仕上げる中綴じ方式 | A4サイズが一般的 | 読みやすく保管もしやすい |
中綴じパンフレットはパンフレット形状の中でも王道の製本です。
「長く使える」「何度も見返される」ことを前提に制作することが多く、以下のようなメリットから選ばれることが多いです。
| 中綴じパンフレットのメリット | 詳細 |
| 情報量を豊富に掲載可能 | 写真や事例、導入のプロセスなどを紹介できる |
| 「保存性の高い資料」としてお渡しできる | 展示会後もじっくり読んでもらえる |
掲載できる情報量が多いため、商品やサービスをストーリー性を持たせた構成で紹介することができます。
展示会後に持ち帰ってその後も長くご使用いただくことを想定して制作するため、以下のような内容で活用される方が多いです。
| 中綴じパンフレットの活用例 | 詳細 |
| 会社案内パンフレット | ストーリー性を持たせた自由度のある構成が可能 |
| カタログ冊子 | 製品ラインナップなど商品の特徴を紹介 |
| プレゼン資料 | 営業・商談用の代わりとしても使用が可能 |
お客様が商品をどのシーンで使用するかなどの紹介を、わかりやすいイメージなどを添えてプレゼンする資料としても活用できます。
基本的には商談スペースなどに常設し、興味を持ってくれた来場者に手渡しをすることが多いです。
リーフレット(折り加工タイプ)|見込み顧客向け
リーフレット(折り加工タイプ)のパンフレットは、様々な形状での制作が可能であり、会社の独自性を演出できる仕様です。

観音開きパンフレットをはじめとした個性的なデザインも制作可能で、折り畳みの方法に応じてページ数が変動します。
| リーフレット種類 | 詳細 |
| ・二つ折り ・観音折り(観音開き) ・蛇腹折り ・巻き三つ折り…など | A4、A5サイズの一枚紙を3面・4面に折り畳み加工 |
リーフレットとは表面・中面で構成されるポケットサイズの印刷物で、中綴じパンフレットと比較すると短納期・低コストでの制作が可能です。
リーフレットタイプは以下の特長からお選びになることが多いです。
| リーフレットのメリット | 詳細 |
| コストを比較的抑えられる | シンプルな形状の場合、コストと準備時間に余裕がある |
| インパクトのあるデザイン | 観音開きや蛇腹折りなど、個性的なデザインも可能 |
二つ折りなど加工の難易度の低い場合、時間やコストを比較的抑えながら準備できることから、中小企業の展示会でも人気を集めています。
情報を絞った訴求で選ばれることが多く、サービスの説明のみなどポイントを抑えた広告物として活用可能で、以下のような例で制作されることが多いです。
| リーフレットの活用例 | 詳細 |
| 特定のサービスや商品紹介 | 打ち出し商材の説明ツール |
| 比較表や料金表 | 他社との比較や導入ステップなどを可視化 |
リーフレットは冊子にはない個性的なデザインで印象付けることができるという特長から、特に打ち出したい商材を記憶に残る形で訴求するのに向いています。
展示会では商談の前後に来場者に手渡し、対話補助のアイテムとして活用することが多いです。
個性的な形状の場合、お話のきっかけとしてもよく使われます。
フライヤー(ペラ)|潜在層との接点づくり向け
フライヤーは1枚で構成されるパンフレットで、折り畳みのないシンプルなデザインです。

「ペラ」と呼ばれることが多く、以下のような特徴があります。
| フライヤー・ペラの特徴 | 詳細 |
| 短納期・低コスト | 断裁以外の加工がないため、コスパ良く制作が可能 |
| 手軽に配布 | 嵩張らない形状でお渡ししやすい |
フライヤーは掲載する情報量は控えめながらも、シンプルな形状のためコスト面で制作しやすく、お客様にもお渡ししやすいのが特徴で、他には以下のような理由から選ばれています。
| フライヤーのメリット | 詳細 |
| 携帯性が高い | シンプルな形状のため手に取るハードルが低い |
簡単な案内や地図付きのガイド、製品ハイライトなどに最適な形状で、具体的には以下のような活用をされることが多いです。
- イベントやキャンペーンの案内
- 目玉商品の紹介用として活用
- 展示会での来場者向けの持ち帰り資料
展示会のお渡し方法としては、チラシスタンドに設置し、セルフでお持ち帰りいただくなど、自由な形式で設置することが多いです。
サッと気軽にお渡しできる形状&サイズ感なので、名刺交換まで至っていない来場者との接点作りに有効です。
展示会のパンフレットの作り方|基本の構成テンプレート
展示会パンフレットの作り方は、基本的に以下の手順で制作を進めていきます。
- ①目的・ターゲットを明確にする
- ②訴求メッセージ・掲載内容を決める
- ③ターゲットに合わせ紙やパンフレットの形式を決める
- ④配布方法・配布場所を設計する
- ⑤配布期間を決める
- ⑥訴求内容をクリエイティブに落とし込む
- ⑦制作会社へ発注する
まずはじめにどんなターゲット層に向けたパンフレットにするのか、そのパンフレットでどんなゴールを目指すのかを設計するのが重要です。
必須項目と掲載順の基本形
パンフレットで掲載する必須項目は以下の通りです。
- 表紙(タイトル・キャッチコピー)
- 課題提起
- 製品・サービス紹介
- ソリューション提案・活用シーン
- 実績・導入事例
- 強み・他社との違い
- 会社概要
- 問い合わせ情報
- 行動喚起
- 裏表紙
以下でどんな内容を掲載するのか、詳細と戦略のコツを解説していきます。
| 項目 | 内容 |
| 表紙 (タイトル・キャッチコピー) | ・企業名 ・製品名 ・心を掴むキャッチコピー ・ブランドロゴ ・魅力的なイメージ写真など |
表紙掲載の戦略
パンフレットの「顔」とも言える部分です。
一目で「どんな会社なのか」「なにを提供しているのか」が直感的に伝わり、読み進めてもらうための興味を強く喚起します。
| 項目 | 内容 |
| 課題提起 | ターゲット層の抱えていそうなお悩みや課題 |
課題掲載の戦略
見込み客の抱えている課題やトラブル例を紹介し、自社商品・サービスで課題を解決!という導線に繋げます。
| 項目 | 内容 |
| 製品・サービス紹介 | ・製品やサービスの特徴 ・具体的な用途 ・性能、仕様 ・導入することで得られるメリット ・実際の導入事例など核となる情報 |
製品・サービス紹介掲載の戦略
来場者が最も求めているのがこの項目です。
競合製品との明確な違いを分かりやすく提示することで、興味関心を深めてもらいます。
| 項目 | 内容 |
| ソリューション提案・活用シーン | どのような課題を解決できるのか、導入後の具体的かつ多様な活用法、未来の展望など価値を提示 |
ソリューション提案・活用シーン掲載の戦略
「導入すると、どんなメリット・未来があるのか?」を具体的に想像してもらうための鍵となる項目です。
お客様の課題に寄り添い、具体的な解決策をわかりやすく提示することで、導入後の利点を明確に示します。
| 項目 | 内容 |
| 実績・導入事例 | 導入企業の名称、導入前後の変化、客観的なデータや数値、写真など |
実績・導入事例掲載の戦略
社会的証明として機能します。
「良く知っている企業が使っている!」という説得力の面で有効な役割を果たします。
| 項目 | 内容 |
| 強み・他社との違い | ・細かな対応力 ・充実したサポート体制 ・費用対効果の高さなど、競合他社との差別化 |
強み・他社との違い掲載の戦略
来場者が数ある出展者のなかから貴社を選ぶ決定打となる情報です。
独自の優位性や他社とは異なる特長を明確に打ち出し、比較検討の材料を提供しましょう。
| 項目 | 内容 |
| 会社概要 | ・会社名 ・所在地 ・設立年 ・代表者名 ・事業内容 ・主要取引先 …など |
会社概要掲載の戦略
企業としての信頼性を保証する基本的な情報です。
来場者に安心感を持ってもらうため、企業の成り立ちや背景を知ってもらい、信頼関係の第一歩を築くための布石とする狙いがあります。
| 項目 | 内容 |
| お問い合わせ情報 | ・担当部署 ・電話番号 ・メールアドレス ・ウェブサイトURL ・QRコード …など |
お問い合わせ情報掲載の戦略
展示会後のフォローアップの起点となる重要な項目です。
スムーズなお問合わせ・商談への導線を設計し、来場者が迷うことなく次の行動に移せるように明確に繋ぐことが重要です。
| 項目 | 内容 |
| 行動喚起 | 「まずはお問合わせください」 「無料相談受付中」 「〇〇をダウンロード」など 具体的なアクションを促す文言 |
行動喚起掲載の戦略
パンフレットを見た人に「行動」を起こさせるための直接的な誘導です。
なにをすればいいのか明確に言葉で指示することで迷いをなくし、反応率を高めます。
| 項目 | 内容 |
| 裏表紙 | ・企業ロゴ ・会社情報のまとめ(簡潔に) ・ウェブサイトやSNSの最新情報など |
裏表紙掲載の戦略
パンフレットを最後まで見た人の心に企業情報を自然に残し、印象を締めくくる最終ページです。
締めにロゴや連絡先を提示することで、記憶への定着を促します。

各掲載項目ごとに、来場者が次の行動に繋がるような仕掛けや工夫が重要です。
展示会のパンフレットで成果を出す設計ポイント
展示会で成果を出すパンフレットは、どんな設計で制作されているのかを解説していきます。
戦略を盛り込んだパンフレットを準備することで、商談を効果的に進めたり、来場者の興味を強く引くポイントとなるので、ぜひ参考にしてみてください。
自社の強みとターゲットを明確にする
自社の強みと見込み客となるターゲット層を明確にすることで、パンフレットは会社紹介に留まらず、受け手の行動を喚起する役割を担います。
制作の際に考えるべき要素
- 見込み客の業種・役職・抱える課題を具体的に設定する
- 課題に対する商品、サービスの価値提供を設定する
- 自社が選ばれる理由を言語化し、制作に落とし込めるようにする
- ペルソナに応じて訴求軸を一本化する
必要な情報を整理して構成に落とし込む
せっかく制作したパンフレットも、構成が曖昧な場合、読み手が迷子になってしまいます。
本当に伝えるべき事柄を厳選し、「あえて削る」勇気が、メッセージの伝達力を飛躍的に高めます。
加えて、構成はアプローチしたいターゲット層に応じて最適化を行いましょう。
例えば、見込み客への訴求を主軸とする場合は、基本情報をわかりやすく提示し、スムーズな行動喚起へと繋げるシンプルな構成が、コンバージョン率を高める鍵となります。
記憶に残るデザインを創り出す
展示会では数多くの資料と比較されるため、瞬間的に「記憶に残る」設計が必須となります。
インパクトのある表紙にすれば、来場者の目にも留まりやすく、自然な会話のきっかけとして活用できます。
制作の際の実践ポイント
- 表紙は3秒で魅力が伝わることを意識する
⇒キャッチコピー+一本化した訴求ポイント、印象的なビジュアルを組み合わせる - 色使いはターゲット層に合わせた工夫を
⇒コーポレートカラー+ターゲット、ブースの印象に合わせたトーンで統一を図る - フォントは読みやすさを最優先に
パンフレットは受け取ってもらっても読んでもらえなければ意味がありません。

デザポケでは、印象的な変形パンフレットのデザインもご提案しています。
他の展示会出展者とは差別化できる、印象に残るパンフレット制作のお手伝いもお受けしております。
CTA(行動喚起)を設けて次のアクションを促す
パンフレット制作の目的は単に”読まれること”ではなく、”次の行動を促すこと”。
パンフレット内で思わず行動を起こしたくなるような工夫を盛り込むことがポイントです。
CTA例による行動喚起の例
- サイトにアクセスして製品動画を視聴する
- 無料相談・サンプル請求を申し込む
- 資料請求やキャンペーンへの会員登録を行う
CTA設計のポイント
- 具体的かつ簡単な行動にすること
⇒5つの簡単な項目記入で資料請求できる、簡単3ステップ・2分で申し込み可能、など - 具体性や特典を添える
⇒パンフレットからのアクセス限定特典など
展示会のパンフレットは自作or外注どちらを選べばいい?
パンフレットの制作方法は、自社で内製化する方法と、専門の業者に依頼する外注化と2種類あります。
どちらがより良い選択なのかは、目的・体制・予算によって異なります。
社内の人的リソースや成果をどのくらい期待するかで判断する場合が多いため、社内把握が重要になります。
判断基準は以下を参考にしてみてください。
自社制作に向いているケース
内製化に向いているのは、以下のようなケースです。
- 制作コストを極力抑えたい
- 広告物の制作に関して、自社で知見がある
- 少部数での印刷を検討している
- 短納期で施策を練りたい
第三者を介さないため、修正や意図の反映を迅速に行える一方で、限られた社内リソースで広告物の制作を行う、あるいは専門的なノウハウが不足している状態では、以下のような多くの課題を抱えることになります。
- デザインやレイアウトの完成度が低いと、信頼感を損なう可能性も
- 内容のブラッシュアップが主観的になりがちで、訴求力が弱まるケースも
制作物のクオリティを重視しつつ、展示会での成果を目指す場合は、プロに依頼する外注化がおすすめです。
また、社内で制作者が複数人いる場合や、担当者が変わると制作物の統一感が失われるというリスクも回避することができます。
外注するメリットと判断基準
パンフレット制作を外注化することの具体的なメリットは、以下の通りです。
- 印刷や仕上がりの品質にある程度の保証がある
- 自社の人員や時間的リソースを節約できる
- マーケティング視点からの提案が得られる
- 仕様・デザインのカスタマイズ性が高い
制作会社はデザイナーやクリエイターチームを抱えているため、美しく訴求力のあるパンフレットの設計ができます。
迷った場合は、以下のチェック項目を確認してみてください。
外注化が向いている場合のチェックポイント
- 自社にデザイナー、クリエイターがいない
- 販促物や広告物の制作経験が浅い
- 展示会の成果にこだわりたい
- 社内の人的リソースが逼迫している
- 印刷部数が1000部を超える想定
上記に当てはまる場合、人的・コスト面を考慮し、外注化がおすすめな場合が多いです。
弊社デザポケでは、ご相談いただいた案件ごと専任の営業スタッフとデザイナーが連携し、制作を進行いたします。
展示会で配布するパンフレットデザインも実績が豊富で、お得なパッケージプランや予算に合わせたご提案が可能です。
これまで培ってきた様々な支援実績を活かし、お客様の課題解決に繋がる最適なご提案をいたします。
展示会のパンフレットに関するよくある質問と回答
展示会パンフレット制作に関するよくある質問と回答をまとめてみました。
展示会での商談の機会損失を防ぐためにも、参考にしてみてください。
展示会パンフレットの部数の決め方は?
パンフレット制作部数は、以下をもとに判断する必要があります。
- 展示会の規模
- 自社のターゲット層の比率
過去に行った展示会の来場者数などのデータから集客目標を定め、必要部数を逆算していく方法がおすすめです。
パンフレットを多く受け取ってもらうには?
パンフレットは単調に配布するだけではなく、お渡しする際の声がけも重要です。
「〇〇のような課題はありませんか?」など、来場者に寄り添った投げかけの言葉を添えることで、興味を引きやすくなります。
人員が足りない場合は、デジタルサイネージや印象的なPOPでの集客の工夫もおすすめです。
伝わるパンフレットで、商談に直結する展示会を目指そう
展示会でのパンフレット制作の重要性や、注意点などをご紹介してまいりました。
展示会でお渡しするパンフレットは、お客様との長期的な関係を築く最初の役割を果たす重要なアイテムです。
記憶に残るデザインは、企業の印象や展示会の成果を大きく左右するため、プロによる設計の工夫が欠かせません。
デザポケは、マーケティング視点とビジュアル視点の双方から、成果に結びつくパンフレットデザインを多くの企業様にご提案しています。
企画からデザイン、製造・納品、その後のアフターフォローまでワンストップで対応できるため、時間とコストを最小限に抑えることが可能です。

広告物でお困りの際は、ぜひ一度お気軽にご相談くださいませ!
紙媒体の関連記事はこちらも