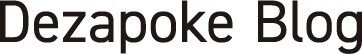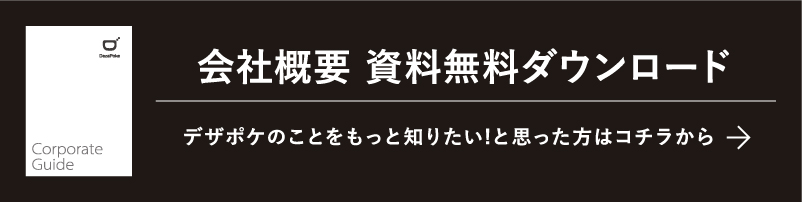カラーユニバーサルデザイン(CUD)とは?身近な事例とIllustratorでの色弱シミュレーション

こんにちは、クリエイティブディレクターのMasaruです。
目次
カラーユニバーサルデザイン(CUD)とは?
私たちが普段あたりまえに使っている「色」。赤・青・緑・黄色といった色彩は、情報を直感的に伝えるうえで非常に強力な手段です。
交通信号、地図の表記、製品のラベル、Webサイトのデザインなど、色を使った情報伝達は日常のあらゆる場面にあふれています。
しかし、誰もが同じように色を認識できるわけではありません。
人によっては特定の色の区別が難しい場合があり、それが生活や仕事の中で不便につながることがあります。
カラーユニバーサルデザインの重要性
CUDの考え方は、日本の研究者・企業・自治体の取り組みによって広がりを見せてきました。
2000年代以降、ユニバーサルデザインの一環として注目され、印刷物やデジタルメディアの世界でも重要なキーワードとなっています。
カラーユニバーサルデザインが対象とするのは主に「色弱(色覚特性)」を持つ人々です。
日本人男性の約5%(20人に1人)、女性の約0.2%(500人に1人)は、一般的な色覚を持つ人と異なる色の見え方をしています。
例えば、赤と緑の区別がつきにくい、濃い紫と青の違いが分かりにくいなど、場面によっては情報が正しく伝わらないこともあります。
ここで重要なのは、「色覚特性を持つ人=ごく一部の例外的な存在」ではないという点です。
教室、会社、店舗、Webサイトの利用者といった場面で、実際に多数の人が該当している可能性があります。

カラーユニバーサルデザインを実現するためには、次のような工夫が必要です。
- 色だけに頼らない情報設計(形・模様・文字を併用する)
- 識別しやすい色の組み合わせを選ぶ(赤と緑は避け、青とオレンジなどコントラストの高い組み合わせを用いる)
- 明度差・彩度差を活用する(色味が似ていても、明るさや濃淡の違いで区別できるようにする)
- 配慮したデザインを確認できるツールの利用(後述するIllustratorなどの機能でシミュレーションする)
このように、CUDは単に「色を見やすくする」だけではなく、情報の伝達精度を高め、ユーザー体験を向上させるためのデザイン戦略といえます。
カラーユニバーサルデザイン(CUD)の身近な例
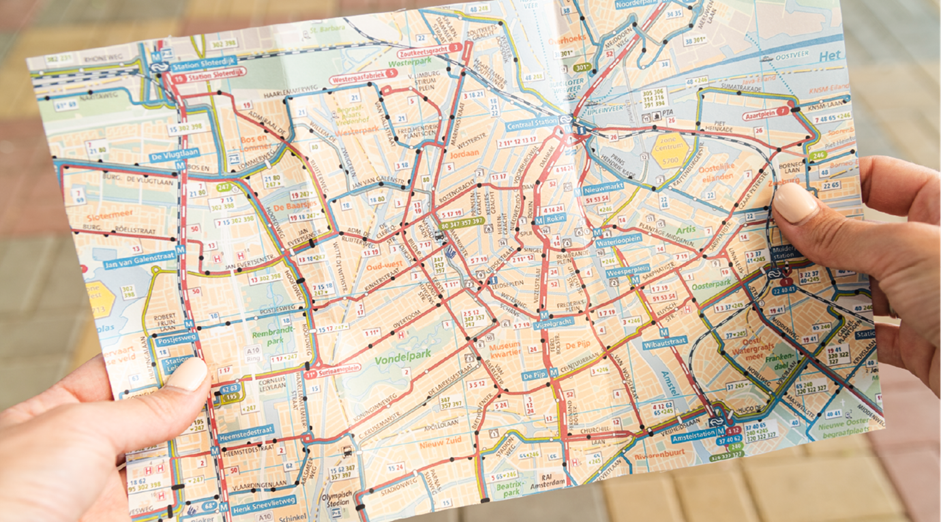
カラーユニバーサルデザインは、学校、市役所、図書館など、あらゆる場所ですでに私たちの身近な環境に取り入れられています。ここでは具体的な事例をいくつか紹介します。
交通信号や標識
最も分かりやすい例が交通信号です。
従来は「赤・黄・緑」の3色で表現されていましたが、緑信号は色覚特性によって赤と区別がつきにくい場合がありました。
そこで近年は「青緑」に近い色に変更されたり、光源に工夫が加えられています。
加えて、信号の配置(赤=上/緑=下)も視覚的な手がかりとなっています。

道路標識でも同様に、色だけでなく形やアイコンを組み合わせることで、誰でも理解しやすいデザインが進んでいます。
地図や路線図
鉄道の路線図や観光地図もCUDの代表例です。
例えば東京メトロやJR東日本の路線図は、複数の色で路線を区別していますが、同時に路線名やアイコン、駅番号を併記しています。
単に色だけで見分けるのではなく、複数の情報を組み合わせることで、より確実に判別できるようにしています。
また観光パンフレットや公共施設の案内図でも、背景色と文字色のコントラストを強めたり、模様を付与して識別性を高める取り組みが見られます。
製品パッケージ
食品や医薬品のパッケージでもCUDの重要性は高まっています。
たとえばアレルギー表示や使用期限などは見落としがあってはならない情報です。
そのため色だけではなく、文字やアイコンによる補助が加えられています。
製薬業界では「誤飲・誤用」を防ぐ目的でCUDの導入が進められており、社会的にも大きな役割を果たしています。
デジタルメディア・Webサイト
Webやアプリの世界では、ユーザーの多様性に応えるためにCUDが積極的に導入されています。
フォームのエラーメッセージを「赤文字だけ」で表示するのではなく、アイコンや説明文を併用する。
グラフを色分けする際に、同時にパターンやラベルを加える。
これらはすべてCUDの考え方に基づく工夫です。

こうした事例から分かるように、CUDは「特別なもの」ではなく、私たちの生活やビジネスにすでに根付いているデザイン哲学なのです。
Adobe Illustratorの色弱シミュレーション機能

デザイナーにとってCUDを実践するうえで欠かせないのが「検証ツール」です。
紙や画面上で作成したデザインが、色覚特性を持つ人にどう見えるのかを事前に確認できるかどうかで、成果物の質は大きく変わります。
Adobe Illustratorには、そのための便利な機能が標準で搭載されています。
それが「校正設定(Proof Setup)」にある色覚シミュレーションです。
利用方法
①Illustratorで制作中のファイルを開く
②メニューから [表示]→[校正設定]→[色覚シミュレーション] を選択
③以下の種類を選べる
- 1型2色覚(Protanopia):赤の感度が弱い
- 2型2色覚(Deuteranopia):緑の感度が弱い
- 3型2色覚(Tritanopia):青の感度が弱い
これにより、デザインがどのように見えるかを画面上で即座に確認できます。
例えば、赤と緑の区別がつきにくい場合、強調したかったボタンが背景とほぼ同化してしまう、といった課題が明らかになります。
デザイン調整のポイント

シミュレーションで問題が見つかった場合は、以下の工夫が有効です。
- 色の組み合わせを変更する(青×オレンジなど、識別性の高い配色へ)
- コントラストを強める(明度差・彩度差を利用)
- アイコンや文字情報を追加する(色以外の手がかりを増やす)
- パターンや線種を組み合わせる(グラフやチャートに有効)
こうした調整を行うことで、色覚特性を持つ人だけでなく、すべてのユーザーにとって情報が伝わりやすいデザインになります。
実務への活用
デザイナーや企業がCUDを意識することは、社会的な責任の一部ともいえます。
特に広告、パッケージ、公共物のデザインは、不特定多数の人々が利用するため、誤認識を防ぐことが重要です。
Illustratorのシミュレーション機能は、その第一歩として非常に有効なツールです。
まとめ
カラーユニバーサルデザインは、色覚の多様性に寄り添い、誰もが正しく情報を受け取れるようにするためのデザイン思想です。
交通信号や路線図、パッケージ、Webなど、すでに幅広い分野で取り入れられています。
そしてデザイナーにとっては、Adobe Illustratorの色覚シミュレーション機能などを活用することで、実務に落とし込むことが可能です。
CUDは「一部の人のため」ではなく、「すべての人にやさしいデザイン」を目指す上で不可欠な考え方です。

株式会社デザポケでは、このようなユニバーサルな視点を持ちながら、より多くの人に届くデザイン制作を心がけています。
お客様のニーズや意図を組んだ制作物のお手伝いもできますので、お困りの際はお問合わせください!