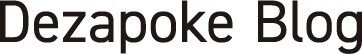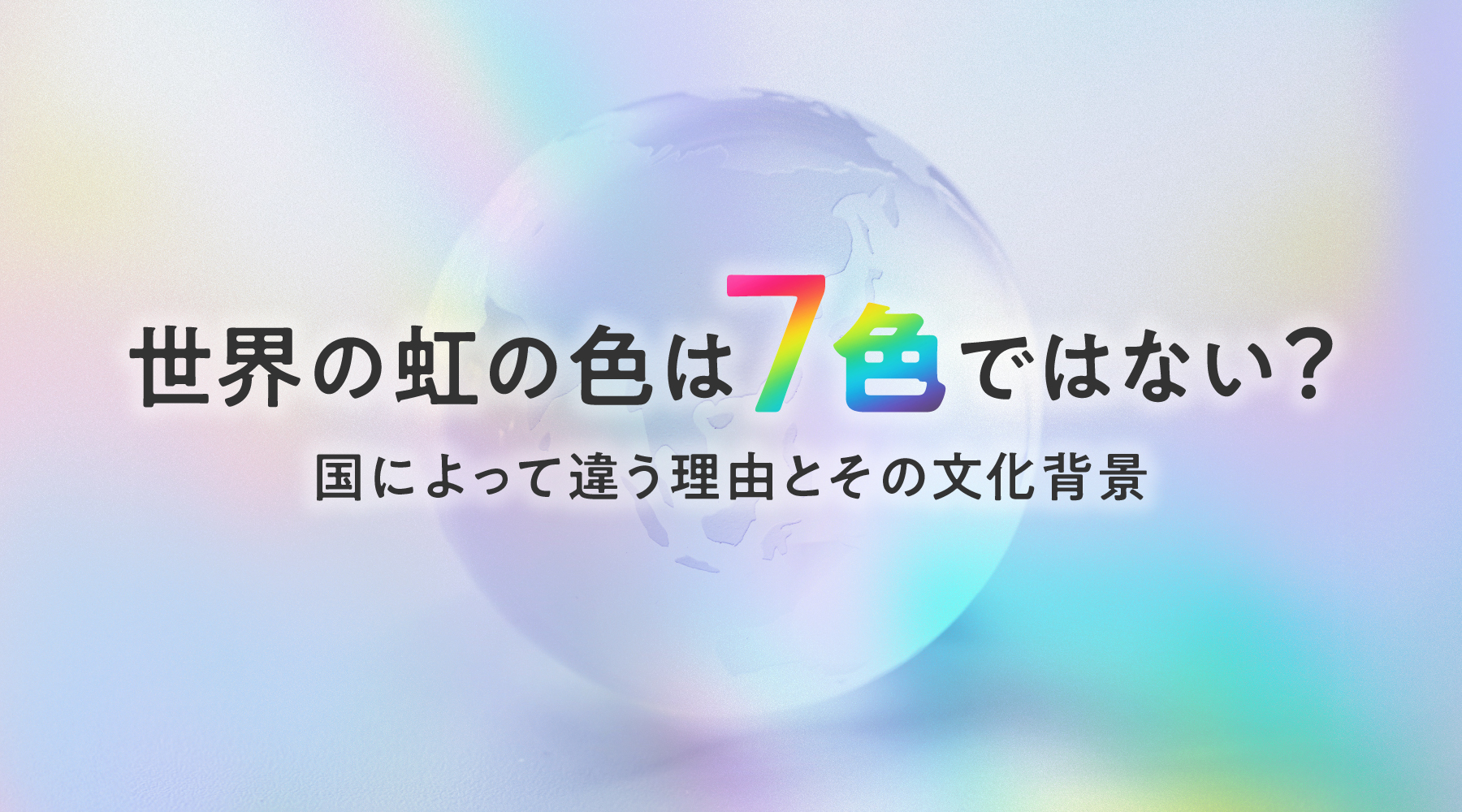
世界の虹の色は7色ではない?国によって違う理由とその文化背景
こんにちは。デザポケ企画営業部のSayokoです。
大学時代に民俗学を専攻し、興味深い!と思った「世界の虹の見え方」についてまとめています。
こちらの記事では、
・虹の色の基本知識
・世界各地での虹の見え方
・虹の文化的背景
について解説しています。
デザインで色彩やモチーフを考える際の一助になれば幸いです。ぜひ覗いていってみてくださいね。
目次
虹の色が世界で異なる理由とその文化背景

虹は、空にかかる美しい自然現象ですが、その色の認識は地域や文化によって異なることがあるのはご存じでしょうか。
例えば、西洋文化では虹の色は「①赤②橙③黄④緑⑤青⑥藍⑦紫」の七色とされています。
一方で、いくつかのアジアの文化では、虹に含まれる色の数が異なる場合があり、こういった違いは、言語や文化的背景に密接に関係しています。
さらに、虹に対する象徴的な意味合いも国や地域によって異なります。
一部の文化では、虹は希望や幸運の象徴とされていますが、他の国では、神話や伝説に根ざした特別な意味を持つこともあり、虹は世界の多様性を映しているモチーフとして、たいへん興味深いものです。
デザインを考案する上で、見る人によって捉え方が異なる、という視点は重要なことですよね。
虹の色の基本知識
虹は、雨上がりの空に見られる現象で、太陽光が水滴に屈折・反射することで現れます。
この過程で、光がスペクトルに分かれ、色が生じます。
一般的には、
①赤②橙③黄④緑⑤青⑥藍⑦紫
の、七色から成り立ち、これを「虹の七色」と呼びます。
虹の色は、それぞれ異なる波長を持っており、赤が最も長い波長で、紫が最も短い波長とされています。
このため、赤から紫に向かって色が並ぶ時、赤が外側、紫が内側に位置することが特徴です。
さらに、虹は二重の虹が現れることもあります。
外側(副虹・ふくこう)の虹が薄くなり、内側(主虹・しゅこう)の虹が鮮やかに見える現象は、技術的には光の屈折と反射によるものです。
いわゆるダブルレインボーは、「願い事がかなう前兆」や「幸運を招く」など、幸運のサインである言い伝えが多く、幻想的な二重虹は縁起物として昔から愛されています。
虹の色はなぜ見えるのか
虹の色が見える理由は、太陽光が雨滴に入ることで生じる光の屈折と反射によります。

太陽光は、実は白色光であり、さまざまな色が混ざった光です。
この光が水滴に入ると、屈折角が異なるために色が分かれ「分散」を起こします。
分散した光は、水滴の内側に反射し、もう一度水滴表面で屈折して出てくるわけですが、この過程で光が波長ごとに分かれるため、我々が見るカラフルな虹が形成されます。
具体的には、赤色が最も波長が長く、次に橙色、黄色、緑色と続き、最も波長の短い紫色が内側に位置します。
虹の色の順番とその理由
虹の色は常に同じ順番で現れますが、その理由は光の波長によるものです。
虹に見られる赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の順番は、光の屈折と反射によって決まります。
太陽光は白い光に見えますが、実際には様々な色の光が組み合わさっています。
それぞれの色は異なる波長を持っており、波長が長い順に「赤、橙、黄、緑、青、藍、紫」となります。
虹が形成される際、水滴の中で光が屈折することで、様々な色が分かれます。
すると、波長の長い赤が最も外側に配置され、次いで橙、黄、緑、青、藍、紫と続いていきます。
この分かれ方は、光の屈折率が波長によって異なるため、色の順番が一定になるのです。
虹の色の順番は、自然の物理法則に基づいて形成されていて、規則性があることがわかります。
世界各地での虹の色の捉え方
虹の色の捉え方は、文化や地域によってさまざまで、共通ではありません。
例えば、西洋の多くの国では、「①赤②橙③黄④緑⑤青⑥藍⑦紫」という七色の帯として表現されることが一般的です。
この色の分類は、万有引力で知られるアイザック・ニュートンが光の分光を発見した結果、広く知られ定着するようになりました。
ニュートンが発表するまで、虹は「3色」または「5色」と考えられることが多かったようです。
一方で、アジアの一部の文化では虹の色の数は異なります。
現代日本では一般的に7色と広まっていますが、一部のアジア圏文化では2~5色という地域も存在します。
虹の色をどのように捉えるかは、それぞれの文化の影響を受けており、地域ごとの独自の視点を反映しています。
単なる科学的現象ではなく、各地の文化を理解する上でも興味深い自然現象と言えますよね。
日本での虹の色の捉え方
ご存じの通り、日本では現在、虹の色は一般的に、虹は赤・橙・黃・緑・青・藍・紫の7色と認識されています。
よく子どもが虹の絵を描いたときに使う色の構成もこちらが多いですよね。
一方で、意外にも日本の古典文学で”虹”はあまり多く登場せず、古来から虹が多色であった認識は薄いようです。
江戸時代の浮世絵には虹が描かれたものがありますが、それらに描かれている虹の色は3色程度(思っていたより少ないですよね…!?)で、当時は7色すべてを認識していなかったと考えられます。
下の浮世絵は1856年・江戸時代に描かれた歌川広重の作品ですが、虹にはほとんど色がついていないように見えます。

歌川広重 六十余州名所図会 対馬 海岸夕晴(1856年)
出典:The Met – Tsushima Kaigan Yubare
虹の色を3~5色と捉えていた日本人が7色と捉えるようになったのは、ニュートンの虹の研究に由来する学校教育が影響していると考えられています。
十二単など着物の配色美に繊細な日本人ですが、虹に関しては7色が定着したのが個人的な予想より遅く驚きました。
アメリカでの虹の色の捉え方
アメリカでは、アイザック・ニュートンの研究に基づき、虹の色は一般的に「①赤②橙③黄④緑⑤青⑥藍⑦紫」という7色として捉えられています。(アメリカは虹6色だ!、という説もあるようですね)
アメリカ文化において、虹は希望や多様性の象徴でもあります。
特に近年では、LGBTQ+コミュニティのシンボル(レインボーフラッグ)としても用いられるようになり、多くの人々にとって親しまれる意味を持つようになっています。
虹は様々な色を含みますが、それらはすべて太陽の白色光から派生したものであり、人によって見え方も異なれば、各色に明確な線引をすることもできません。
何より、どの色に優劣をつけることができないことから、虹は「多様性」や「共存」「自由」といったシンボルとしての役割を持っています。
ヨーロッパでの虹の色の捉え方
ヨーロッパでは、虹の色は一般的に「①赤②橙③黄④緑⑤青⑥藍⑦紫」の7色として捉えられていますが、イギリスは藍色がない6色として認識されているようです。
また、ヨーロッパの文化においては、虹はしばしば希望や祝福の象徴とされています。
例えば、神話や伝説の中に虹が登場することが多く、神々の使いとして描かれることも。
特に、ギリシャ神話ではゼウスに仕えた虹の女神イリスが登場し、女神たちの間を結ぶ使者として重要な役割を果たしています。
ヨーロッパでの虹の色の捉え方は、科学的な理解と文化的な象徴が結びついて形成されており、人々にとって特別な意味を持つ現象となっているのが興味深いですね。
アジア・アフリカなど他地域での虹の色の捉え方
アジアやアフリカの文化において、虹の色の捉え方は西洋と異なる場合があります。
アフリカの多くの地域では、虹は特別な象徴を持つ存在として認識されています。
例えばいくつかの部族では、虹は神々からのメッセージや幸運をもたらす現象と考えられています。
そのため、虹が現れた際には、特別な儀式や祝祭が行われることもあり、単なる自然現象ではなく、文化や宗教の中で重要な位置を占める存在だということがわかります。
台湾やアフリカの一部部族は3色と捉えている地域にあり、国や文化によってかなり幅があることに驚きました。
学生時代に受講した文化人類学の授業で、ミャンマーのある地域に住むカヤン人という種族が虹は2色だと捉えている、という内容で、7色は万国共通の認識ではないのか…と衝撃を受けました。
暖色と寒色のみの色彩言語の世界では、虹は2色に分けられるようです。
境界がはっきりしない虹の色彩は、中間の色を表す言葉が存在しない人々には極めてシンプルに表現されることを知り、新鮮に感じました。
虹の色の文化的背景
虹の色には、それぞれ独自の文化的背景が存在します。

西洋では、虹はニュートンの色彩理論によって七色が定義され、多くの人々に親しまれています。
虹の色は希望やハーモニーの象徴としても現代で親しまれています。
虹が特別な意味を持つ例は多く、例えば、アフリカの一部の部族では、虹は神々のメッセージとされ、何か特別な出来事の前触れと考えられています。
虹の色は単なる自然現象ではなく、文化や歴史に根ざした深い意味を持っているのです。
歴史的背景
歴史的背景から見ても、虹は古代から現代にかけてさまざまな文化において特別な意味を持ってきました。
古代文明では、自然現象としての虹に神聖視が伴い、神々からのメッセージや予兆と考えられることが多かったのです。
例えば、ギリシャ神話では、虹は天と地を繋ぐ架け橋とされ、神々の恩恵を象徴する存在でした。
現代においても、虹の多様な解釈は教育やアート、さらには LGBTQ+コミュニティのシンボルとして、広がり続けています。
虹は単なる美しい自然現象にとどまらず、歴史と文化の詰まったシンボルとも言えるでしょう。
宗教的背景
虹は多くの宗教において重要なシンボルとされています。
特に、キリスト教においては、虹は神とノアの約束の象徴として描かれていました。
大洪水の後、神がノアに与えた虹は、二度と地上を洪水で滅ぼさないという約束を示しており、希望や和解の象徴とされています。
虹は新しい世界の始まりにおいて結んだ契約と祝福のしるしとして、時代や地域を超えて人々の心に希望や意味を与え続けてきたことがわかります。
また、仏教やヒンドゥー教においても虹は特別な意味を持つことがあります。
仏教圏内においても、虹は神聖視されており、釈迦が天上界から降りてきた際に虹が関わっていた、という伝承があるようです。
チベット仏教では「虹の身体」と名付けられた瞑想体験があり、仏画などにもよく虹が描かれています。
教育的背景
自然科学では、虹の形成過程を学ぶことによって、光の屈折や反射の原理を理解することができます。
虹の発生を理解することによって、物理学や光学への理解が深まることが期待できます。
さらに、虹を通じて多文化教育への助けも期待できるでしょう。
異なる文化における虹の意味や歴史を学ぶことで、子どもたちは多様性の理解を深めることができ、異なる視点を尊重する心を育む手助けとなるのではないでしょうか。
虹の色に関するよくある疑問&質問

虹の色に関する質問は多岐にわたりますが、ここではよくある質問をいくつか取り上げます。
虹の色は本当に7色なのか?
虹の色は一般的に赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の7色として知られていますが、実際には虹の色の境界は曖昧です。
7色というのは、主にアイザック・ニュートンが提唱し、目視で認識しやすい色のグループに分けられた結果によるものです。
実際には、光は無限に近い色のスペクトルを持ち、それぞれの色が滑らかに移行しています。
たとえば、青と藍の間には多くの色合いが存在することから、虹の色を7色に限るのはあくまで便宜上の分け方に過ぎません。
文化や地域によっては虹の色を異なる数で認識することもあり、特にアジアの一部地域などでは2色~5色で表現されることもあります。
虹の色の覚え方
世界各国で虹はどのように覚えられているのかを調査してみました。
日本での虹の色の覚え方
一般的に7色と認識されている虹の色。
日本では、松田聖子さんのファンの方は『硝子のプリズム』という曲にこの「赤・橙・黄・緑・青・藍・紫」という歌詞が出てくるので、覚えていることもあるのだとか。
日本ではほかに「七色の虹」の覚え方として、「赤・橙・黄・緑・青・藍・紫」を音読みで「せき・とう・おう・りょく・せい・らん・し」と唱える方法が親しまれています。
アメリカでの虹の色の覚え方
一方、アメリカでは7色を構成している
・赤(red)
・橙(orange)
・黄(yellow)
・緑(green)
・青(blue)
・藍(indigo)
・紫(violet)
の頭文字を紫から順につなぎ合わせ、「VIBGYOR」として覚える方法が知られているようです。
イギリスでの虹の色の覚え方
イギリスやオーストラリアでは以下の英文で虹の色を覚えるようです。
Richard of York gave battle in vain.
(ヨーク公リチャードは戦争を仕掛け、失敗した)
15世紀後半にイギリスで起こった「薔薇戦争」の際、ヨーク公リチャードが王位継承権を主張して反乱を起こし、奮闘するも討ち取られてしまった、という史実に基づいているこちらの一節。
こちらも色の頭文字を組み合わせ覚える方法なんだとか。
・Richard→Red
・of→Orange
・York→Yellow
・geve→Green
・battle→Blue
・in→Indigo
・vain→Violet
虹の色も歴史も学べるお得な例文ですね。
まとめ
単なる気象現象を超え、社会的なメッセージを伝える重要なシンボルとなっている虹。
広告デザインやアイコンにもよく使われているモチーフですが、時代や地域によって様々な意味を持っている、とても興味深いシンボルでした。
現代日本に住む私たちが一般的に知っている虹の七色は、西洋文化に基づいていることがわかりましたが、他の地域では異なる認識が存在します。
特にアジアのいくつかの文化では、虹の色数やその表現が違うこともあるため、多様性が重んじられる現代では、こうした違いを理解することが求められます。
視覚的な美しさだけではなく、背後にある文化的な意味を汲んだうえで、さまざまなデザインに生かしてみてはいかがでしょうか。